「1.5キロって歩いたら何分くらいかかるんだろう?」と思ったことはありませんか。
地図アプリや物件情報でよく見る距離ですが、実際に歩くと意外と感覚が違うものです。
この記事では、1.5キロを歩くのにかかる時間を、速度別・シーン別にわかりやすくまとめました。
また、歩数の目安や、通勤・買い物など日常の移動シーンごとのリアルな時間感覚も紹介します。
「1.5キロ=何分くらい?」がひと目でわかる内容になっていますので、予定を立てる際の参考にしてみてください。
1.5キロ歩くと何分かかる?実際の目安をシーン別に解説
1.5キロの距離は、駅から自宅やスーパーまでなど、日常の移動によくある長さです。
ここでは、歩く速さの違いや環境によってどのくらい時間が変わるのかを、できるだけ実際の感覚に近い形で解説します。
一般的な歩行速度で計算した場合
多くの人が平らな道を歩くときの速さは、おおよそ時速4〜6kmです。
この速度をもとに計算すると、1.5キロを歩くのにかかる時間は次のとおりです。
| 歩行速度 | 所要時間(目安) |
|---|---|
| 時速6km(速め) | 約15分 |
| 時速5km(普通) | 約18分 |
| 時速4km(ゆっくり) | 約22.5分 |
つまり、1.5キロは平均で20分前後と考えておくと実用的です。
もちろん、歩き慣れている人や坂道・信号の多いルートなどによっても前後します。
不動産広告などで使われる「徒歩何分」基準とは
不動産業界では、「徒歩1分=80メートル」という計算が一般的に使われています。
この基準で1.5キロを計算すると、1500メートル ÷ 80メートル = 約19分。
この19分という数字は、一般的な成人が平地を一定ペースで歩く速度を想定しています。
したがって、地図アプリや住宅情報サイトで見かける「徒歩◯分」は、ほぼこの基準をもとにしています。
信号待ちや坂道がある場合はどのくらい増える?
都市部などで信号が多い場合、立ち止まる時間を加えると約2〜3分ほど余分にかかることがあります。
また、坂道や段差が多い道では、距離は同じでも体感的な負担が増え、結果として所要時間も長くなりがちです。
| 環境条件 | 追加時間の目安 |
|---|---|
| 信号が多い道 | +2〜3分 |
| 上り坂が多い | +3〜5分 |
| 人通りが多い | +1〜2分 |
つまり、現実的には15〜25分の範囲で見ておくのが安心です。
予定や約束に遅れないよう、余裕を持った移動計画を立てるのがおすすめです。
1.5キロを歩くとどのくらいの歩数になる?
1.5キロという距離を歩くとき、どのくらいの歩数になるのか気になりますよね。
ここでは、平均的な歩幅をもとに、身長や性別などによって変わる歩数の目安をわかりやすく整理します。
平均的な歩幅から算出した歩数の目安
成人の平均的な歩幅はおよそ70〜75センチとされています。
これをもとに、1.5キロ(=1500メートル)を歩く場合の歩数を計算してみましょう。
| 歩幅 | 歩数(1.5kmあたり) |
|---|---|
| 70cm(小柄な人) | 約2140歩 |
| 75cm(平均的) | 約2000歩 |
| 80cm(大柄な人) | 約1875歩 |
このように、歩幅が5センチ違うだけでも1.5キロで200歩以上の差が生まれます。
そのため、アプリや万歩計を使って歩数を計測するときは、実際の歩幅に合わせて設定しておくとより正確です。
身長や性別でどのくらい変わるのか
歩幅は体格によって変化します。一般的に、身長が高いほど一歩の長さも自然と伸びます。
| 身長 | 平均歩幅 | 1.5kmの歩数 |
|---|---|---|
| 150cm | 65cm | 約2300歩 |
| 160cm | 70cm | 約2140歩 |
| 170cm | 75cm | 約2000歩 |
| 180cm | 80cm | 約1875歩 |
このように、同じ1.5キロでも人によって最大400歩近い差が出ることがあります。
おおよその目安として「1.5キロ=約2000歩前後」と覚えておくと便利です。
1.5キロを歩く時間の「現実的な感覚」
数字で見ると1.5キロは短く感じますが、実際に歩くと「思ったより遠い」と感じる人も多いです。
ここでは、通勤や買い物などのシーン別に、体感的にどのくらいの距離・時間に感じるのかを解説します。
通勤・通学の距離としての目安
通勤や通学の道として1.5キロを歩く場合、片道の目安は約20分です。
地図アプリなどで見ると「意外と近い」と思うかもしれませんが、信号や人混みを考慮すると、毎日続けるには少し長めの距離です。
| 移動シーン | 所要時間 | コメント |
|---|---|---|
| 通勤・通学(街中) | 約20分前後 | 信号や人通りが多く、ペースが安定しにくい |
| 住宅街〜駅まで | 約18分 | 信号が少ないため比較的スムーズ |
| 郊外・田舎道 | 約15分 | 信号がほぼなく、歩きやすい道が多い |
1.5キロ=「駅2つ分」または「大通り3本分」ほどの感覚で考えると、距離のイメージがつきやすいでしょう。
買い物・散歩・お出かけなどの体感時間
目的が買い物や用事の場合、同じ距離でも「体感時間」が変わります。
立ち寄りや荷物の有無によって、ペースが自然に遅くなるからです。
| シーン | 平均時間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 買い物や外出 | 約25分 | 荷物や立ち止まりで時間が伸びやすい |
| ゆったり散歩 | 約22分 | 景色を見ながら歩くとやや時間がかかる |
| 急ぎの移動 | 約15分 | 信号や混雑が少なければ最短に近づく |
つまり、同じ1.5キロでも「目的」によって5〜10分ほど差が出るのが一般的です。
「急いで歩くと約15分」「寄り道ありなら25分」という感覚で覚えておくと便利です。
1.5キロの移動時間を短縮するコツ
同じ1.5キロでも、歩き方やルートを工夫するだけで時間を短縮できます。
ここでは、日常の移動を少し効率化するための実践的なポイントを紹介します。
効率よく歩くためのペースと姿勢
歩くスピードを上げるには、まず「一定のリズムで歩く」ことが大切です。
途中でペースを変えるよりも、安定したテンポを保つ方が結果的に速く到着します。
| コツ | 理由 |
|---|---|
| 腕を自然に振る | 歩幅が広がり、テンポが安定する |
| 背筋を伸ばす | 姿勢が整い、足の運びがスムーズになる |
| 視線をやや遠くに | ルート全体を把握しやすく、歩きやすい |
また、足を強く蹴り出すよりも、「軽く前に進む意識」で歩くと疲れにくく、スピードを維持しやすくなります。
無理に速く歩くより、一定ペースを保つことが結果的に最短時間につながるのです。
歩きやすい靴やルート選びのポイント
歩行時間を短くするためには、靴とルートの選び方も大きく影響します。
例えば、靴底が柔らかすぎると安定感がなくなり、結果的にスピードが落ちてしまいます。
| ポイント | おすすめの考え方 |
|---|---|
| 靴の選び方 | 底が平らで、かかとがしっかりした靴を選ぶ |
| ルート選び | 信号や段差の少ない道を優先 |
| 時間帯 | 人通りが少ない時間を選ぶとスムーズに進める |
特に街中では、信号や混雑を避けるだけで2〜3分の短縮につながることがあります。
「どのルートを選ぶか」で時間の印象が大きく変わるため、地図アプリを活用して最適ルートを見つけておくと良いでしょう。
まとめ|1.5キロを歩く時間は目的で変わる
ここまで、1.5キロを歩く時間の目安や歩数、シーン別の感覚を紹介してきました。
最後に、全体のポイントを整理しておきましょう。
速さ別の所要時間まとめ
まずは、歩く速さごとの時間を改めて確認してみます。
| 歩行速度 | 所要時間(1.5km) |
|---|---|
| 速め(時速6km) | 約15分 |
| 普通(時速5km) | 約18分 |
| ゆっくり(時速4km) | 約22.5分 |
平均的には20分前後がひとつの目安になります。
信号や坂道がある道なら、余裕をもって25分ほど見ておくと安心です。
移動計画を立てる際のチェックポイント
1.5キロは、地図上では短く見えても、歩くと意外と距離を感じやすい長さです。
予定や時間に遅れないようにするために、次のポイントを意識しておきましょう。
| チェック項目 | 確認のコツ |
|---|---|
| ルートの下見 | 坂道や信号の多い道を避ける |
| 時間の余裕 | 計算時間+5分を目安に出発 |
| 靴と服装 | 動きやすく、気候に合ったものを選ぶ |
「1.5キロ=約20分前後」という感覚を覚えておくと、移動や待ち合わせの計画を立てやすくなります。
時間を読めるようになると、日常の移動がぐっとスムーズになるはずです。

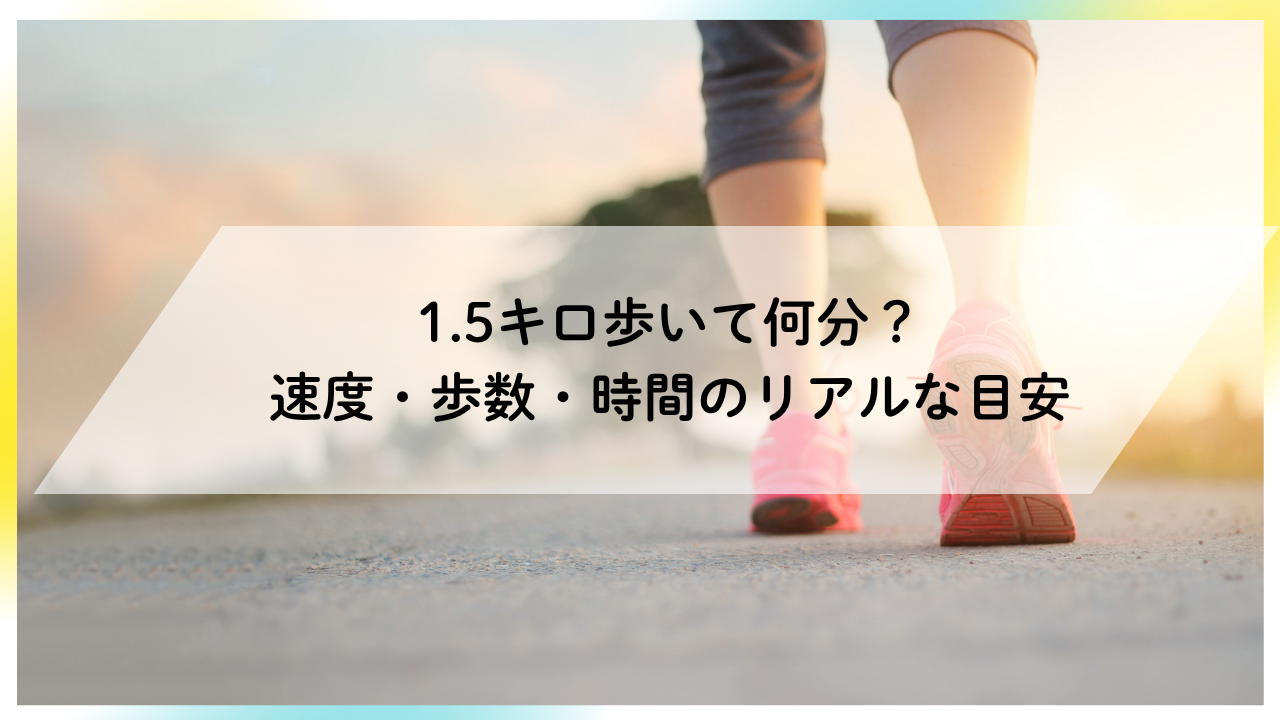
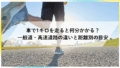
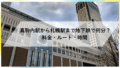
コメント